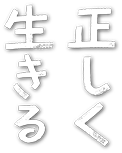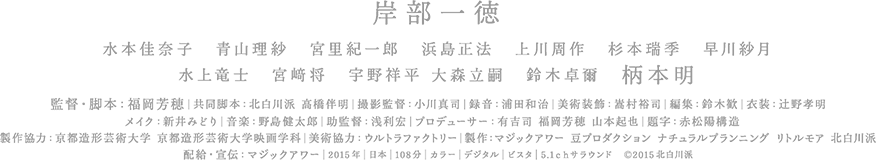「柳田」は私の父親である
福岡芳穂
この映画は、美術家であり大学教授である「柳田」という人物が、自ら創作するオブジェに核分裂反応を惹き起こす物質を仕込み、それによって世界を終わらせようとする話を軸として、様々な人間たちの生が交錯する物語である。
シナリオを読んだときに、或いはこの映画を観たときに、この「柳田」という登場人物が最も「わかりづらい」との指摘を受ける。「柳田」の物語は理解を充足するリアリティを欠いており成立していないという批判である。
その批判を真摯に受け止めつつ、初めてここに明かす。
「柳田」は、私の父である。
他の登場人物たちは、一緒にこの映画を作ってきた学生たちとともにリサーチや想像を重ねて創り上げていった。
だが「柳田」はほぼ一貫して、私の父の姿なのである。
2014年6月に亡くなった父は、さほど有名とは言えないが生涯画家であった。
ダークなアンバーや紺、緑を基調として、打ち棄てられた風景やその中に佇む人々を多く描いた。人物の表情のディテールを描写することはなく、建物の窓や入り口は深い闇に塗り込められている。それでも、そこに生きる人々或いは生きていた人々の時間を、息遣いを充分に想像させた。
或る時には、何気なくそこに佇む人物の目にこちらが射すくめられるような怖ささえ感じた。
冷たく重厚な、と評されることが多かったようだ。しかしその「冷たさ」はけっして「拒絶的」なものではない。ある種の攻撃性或いは挑発性が、観る者への「問いかけ」として静謐の中で逃れようのない重さを伴って表現されているということではなかったか。
私は彼の絵が好きだった。
飛ぶように売れるといった画風ではないので昔から絵を教えて暮らしを立てていて、お弟子さんたちが周りに多くいた。彼らにとっては、紳士的で知的でいつも優しい微笑を湛えた先生であったという。
私の知る父の像は違う。
彼は鬱屈の人であり、頑なな、狷介とも言える性格だったのではなかっただろうか。
反社会的なものを自身の中に常に抱え、攻撃的な姿勢を保持し続けていたように思う。
周囲に阿る、或いは他者の安易な理解を自ら求めるというようなことは一切なかったのではないか。
ずいぶん以前に「四角く黒いリンゴを描け」と言った彼の言葉が忘れられない。
芸術は須らく解放の作業でありどこまでも自由を求め続ける終わりない創造でなければならない、と、彼は私に教えた。同時にそれは限りない破壊でもある、と。
若いころには鬱を患った時期もあると聞いたこともあった。
この映画が動き始めた頃にはまだ生きていた。
病で自由にならない手で、それでも絵を描き続けようとしていた。
最後は一人暮らしの自宅で突然倒れて病院に運ばれ、その後徐々に数か月をかけて意識と言葉の明瞭を失っていった。
病室に行くたびに私は彼にとりとめなく様々なことを話しかけた。それに対する反応も概ねなくなってきた時期に私が答えなど期待もせず、大学の学生たちが、自分たちの作る映画が「わからない」と言われることを非常に恐れるのだと愚痴ったことがあった。
その瞬間不自由な身体に力が入り、発語もままならないはずであった彼が叫んだ。
芸術はわからなくていいんだ!
正解なんてない!
わからなくていいと言い放つ彼の表現を解釈してもしょうがないし、誰しもが彼の絵からそれを感じ取るかどうかはわからないが、彼の表現の持つ攻撃性や観る側に何かを強く問うてくる挑発の「静けさ」は、何に起因したのだろうか。
彼の育ちや環境から生まれたルサンチマンであれば、彼の性格をすればその表現はさらに激しいパッショネイトなものになったはずだろう。
ではその静謐は、何を意図してのものであったのだろうか。
それは憎しみや怨嗟や呪いではなく、祈りではなかったのか。
死ぬ間際に、彼の唇が開き、私を見つめて「あ…」と言った。自分で自身の最期を認めた表情のような気がした。口を動かすだけで言葉にならないその後を私が続けた。
ありがとう?…彼は首を振った。
愛してる?…激しく彼は首を振る。
あんたは(彼は私を「あんた」と呼んでいた)…違う。
あとは…違う。
明日…違う。
あ…の謎。
謎を追いかけ続ける限り、私には私と彼との物語が生まれ続ける。
私は、彼の失われた明日を創造しなければならない。
私は「あ…」について永遠に誤読を繰り返しつつ、彼との物語を更新し続けなければならない。
私にはもうひとりの父親がいた。
2012年10月に亡くなった若松孝二である。
私が映画の世界に入り今こうして生きているのは彼がいたからである。
若松についてここで多くを語る必要はないだろう。
彼もまた、その真意は未だにわからないが私に対して「わかりづらい映画を撮ろう」と言ったことがあった。
彼の存在も、「柳田」という人物に大きく反映されている。
世界はそもそも無根拠である。私たちはその世界を無根拠のままに描かねばならない。そこに何かの解釈を付すことは誠に僭越でかつ愚かなことであるだろうと思っている。
だがそこで人々が生きていることになにがしかの意味があるのだとすれば、それは何かを探し、創りあげねばならないのだろう。
我々は生きており、死者たちもまた我々の物語の中で生きているのだから。
当たり前のことだが、「自分にはわからないもの」を我々は描き始める。
描くことによってさらに解の入り口を探し求め発見しようとする。
そのとき、私たちは映画としてのストーリーをそこに発動させるために登場人物に「行動」をさせなければならない。
選択したその行動自体が正しいのかどうかはいつもわからない。
或いは「柳田」の行動が、この物語にとって正しいものなのかどうかも確信がない。
私のその確信のなさが「柳田」の存在にリアリティを失わせているのだろう。
ただ、私自身は父たちの前で今でも立ち尽くし、彼らが何をやろうとしていたのか、何を私に遺そうとしたのか、彼らが何を見つめていたのかを考え続けてきた、いや考え続けているわけであり。
私はこの映画を、私の父たちと私の子どもたちとの交話にしたいと望んだ。
「わからないもの」を見つめ続けた父たち。「わからないこと」に目を背ける子どもたち。
柳田は、私の父たちなのだ。
2014/12/9